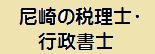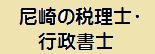
|
 |
平成19年度税制改正 |
中小企業にとって関心の高い改正事項としては、①減税効果の大きい減価償却制度の大幅な見直しが行われること、②資本金1億円以下の法人が特定
同族会社の留保金課税制度の適用対象から除外されること、③特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が見直しされ適用除外基準額(所得金額)
が1,600万円に引き上げられることなどが挙げられます。
与党の平成19年度税制改正大綱のポイントは、以下のとおりです。
|
一 経済活性化・国際競争力の強化
<減価償却制度>
1.残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産について、残存価額を廃止する。
なお、定率法の償却率を「定額法の償却率×2.5」とする改正が行われる模様。
このため、現行の定率法と比較して、使用開始当初の損金算入可能額が大きることが期待できる。
2.償却可能限度額の廃止
平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。
なお、既存設備については、償却可能限度額(取得価額の95%)に到達後5年間で均等償却できることとする。
3.法定耐用年数の見直し
フラットパネルデイスプレイ製造設備(10年→5年)など3設備の法定耐用年数を短縮する。
なお、平成20年度税制改正に向け、減価償却資産の使用の実態等について更に調査・分析を進め、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の
短縮特例制度の手続簡素化について検討する。
4.固定資産税の償却資産
固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格をふまえ、現行の評価方法を維持する。
平成19年4月1日改正法施工前・施工後に取得した減価償却資産は、上記の通り計算方法が異なることもあり、従来以上に資産管理に気をつけなければ
ならない。
<中小企業・ベンチャー支援>
1.特定同族会社の留保金課税制度の見直し
特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金1億円以下の法人を除外する。
2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
3.取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、60歳以上の親
からの贈与についても、一定の要件の下で、相続時精算課税制度の適用を認めることとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の
措置を講ずる。
二 金融・証券税制
上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%・住民税3%)
の特例の適用期限を1年延長する。
具体的には、上場株式等の配当(大口以外のもの)は、平成20年3月31日⇒平成21年3月31日に延長されます。
上場株式等に係る譲渡所得(譲渡益)は、平成19年12月31日⇒平成20年12月31日に延長されます。
三 住宅・土地税制
<住宅税制>
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を
創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率
については、次のとおりとする。
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
| 平成19年 |
15年間 |
2,500万円以下の部分 |
1年目から10年目まで0.6%
11年目から15年目まで0.4% |
| 平成20年 |
同上 |
2,000万円以下の部分 |
同上
|
|
四 円滑・適正な納税のための環境整備
1.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を
付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除する。
なお、平成19年度分の本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできないこととする。
↓
(注)この5000円の所得税の控除を受けるためには、個人が電子証明書-住基カード(1000円)を取得することが前提。このカードは数年に一度更新しなければなりません。
2.税務手続の電子化促進措置
(1)電子申告における第三者作成書類の添付省略
所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、医療費の領収書などの第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、
送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。
(2)電子署名の省略
電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及び電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである
場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
①税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者
②源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
③税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者
(注)上記①及び②の改正は平成19年1月4日以後に、上記③の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用
する。
*税理士による代理送信では、納税者の電子署名が省略可能となりますので、納税者が電子証明書の取得及びICカードリーダライターの購入をする必要は
ありません。
(3)電子証明等証明制度の創設
電子情報処理組織により申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織により行った一定の申請等の日付、名称及び
その送信した内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について適用する。
五 その他
1.寄付金控除の引上げ
控除対象限度額を総所得金額等40%(現行30%)に引き上げる。
2.役員給与の整備
法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。
(1)定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。
(2)事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務
の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が
定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出を不要とする。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |