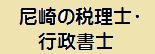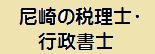
|
|
いったん作成した遺言を
撤回できますか?
|
「遺言書を書いたけれど財産の承継者を変えたい」「子が結婚したり孫ができたりして家族構成が変わった」「新たな資産の取得があり遺言書にその資産が記載されていない」など、せっかく作成した遺言を撤回したり、取り消したいと考えることも少なくありません。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法985条)としていますので、遺言者が生前中で、かつ、意思能力があれば、自由に撤回・取消ができます。
この遺言の撤回には、3つの方法があります。 |
| |
| ①後の遺言で撤回する方法-後遺言優先の原則(注)- |
| 新たに遺言をして、その遺言書の中で前の遺言を撤回すると表明する方法です。直接で最も明確な方法です。公正証書遺言を撤回する場合、公正証書番号や作成年月日、公証人の名前などを記載して撤回する旨を書くようにします。 |
| 公正証書遺言を撤回するのには、自筆証書によっても行うことができますが、撤回の信憑性が疑われる恐れもありますので、後の遺言は公正証書のような、より厳格な方法ですることをおすすめします。 |
 |
| |
(注)「後遺言優先の原則」について
先の遺言と後の遺言の内容が抵触する時には、抵触する部分について後の遺言が優先します。
そのため、最初の遺言で「預貯金は妻に相続させる」となっており、次の遺言で「土地建物は長男に相続させる」となっていれば2通とも有効です。
同じ日付の場合には、時間的に後のものが優先します。遺言書に時間まで記入してあればよいのですが、そうでないときには記載上、あるいは記載外の事情によってどちらが後かを決めることになります。 |
| |
| |
| ②遺言書を破棄する方法
|
|
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。しかし、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されていることから遺言書を破棄したことにはなりません。
|
| |
| ③遺贈の目的物を破棄又は生前に処分する方法 |
| 遺言者が遺贈の目的物を破棄したときは、遺言を撤回したものとみなされます。たとえば、古い建物を取壊して新しい建物を建てた場合には、遺言は撤回されたものとみなされますので、誤解を招かないためにも新たに遺言をし直すべきです。また、遺贈の目的物を第三者に譲渡したときも遺言を撤回したものとみなされます。 |
|
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |