|
|||
|
|||
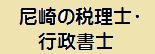 |
遺言書-包括遺贈と特定遺贈 遺贈とは、遺言により被相続人の財産を相続人、相続人以外の人や、法人に無償譲与することをいいます。遺贈する人を遺贈者といい、それを受ける人を受遺者といいます。なお、遺贈には、以下で説明する包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。 ②包括遺贈 遺産の全部・全体に対する配分割合を示してあげることです(民法964)。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます(民法990)。なお、次に説明する特定遺贈と違い、遺産を配分する割合を決めて財産をあげるので時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。 ③特定遺贈 遺産のうち特定の財産を示してあげることです(民法964)。たとえば、「どこそこの土地をAにあげる」、「この株式をBにあげる」というようなことです。財産が明確なので、遺言も執行されやすいです。なお、財産が特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないようにしてください。財産が特定されているため、包括遺贈と違い、受取人が借金を引き継ぐリスクがないです。ただし、遺言書の作成から相続までが長期間ですと、遺贈する財産を処分してしまう場合などがあり、その場合、遺言は無効になります。そのため、遺贈する予定だった財産を処分してしまうなど遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。 ④包括遺贈と特定遺贈の違い
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~ 【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他 【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |