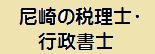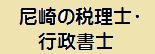
|
改正民法は、平成29年6月2日に公布されましたが、その施行は平成32年4月頃となる模様です(公布時の状況)。公布から施行までに3年もの期間が置かれているのは、今回、契約に関する規定が大きく見直され、特に事業者にとって、改正への対応・準備に時間を要する重要な項目が少なくないからです。
なお、改正民法が施行されるまでは、現行の民法の規定が適用されることになるので、注意が必要です。
|
|
|
| 現行民法の規定は? |
会社を経営する親戚や知人から、銀行借入れの保証人を依頼され、断り切れずに引き受けたために、後で膨大な債務を肩代わりすることになり、生活破綻に追い込まれたといった悲劇が後を絶ちません。しかし、中小企業の場合、財務諸表の信頼性が必ずしも十分とはいえない、あるいは担保とするだけの財産の保有がないなどの事情から、金融機関としては融資に当たって個人保証を求めざるを得ないケースが少なくないことも事実です。
現行の民法には、個人保証の安易な引き受けへの大きな歯止めとなる規定がありません。そのため、金融庁は、金融機関に対して、監督指針等を通じて、経営に関与しない第三者に連帯保証を求めないよう指導しています。 |
| 改正民法ではどうなる? |
| 上記のような背景を考慮して、今回の民法改正では、次のような制約が設けられました。 |
①個人保証の制限
◆経営にタッチしない第三者(個人)が保証人となる場合に一定の要件を義務づける規定の新設。 |
②個人保証人の保護
◆個人保証を依頼する際にその相手への情報提供を義務づける規定の新設。 |
|
①個人保証をするには公正証書が必要に
i)規制の対象
法人や個人事業者が金融機関等から借り入れる「事業用資金」の個人保証
ii)規制の内容
保証人になろうとする者(個人)が、保証契約の締結前1ヶ月以内に、公正証書で「保証債務を履行する意思」を表示していなければ、保証契約は原則として無効とされます。
つまり、債権者(金融機関等)との保証契約を結ぶ前に、保証人になることを依頼された人が公証役場に赴き、公証人の前で、融資を受けた事業者が債務を履行しない場合は自分(保証人)がその債務の全額を履行する意思を示して、公正証書を作成することを義務づけるわけです。情に流されて安易に個人保証を引き受けることを防ぐため、契約の前に、個人保証の重大さを認識し、慎重に意思決定してもらうことが、この規制の目的です。
iii)規制の例外
この規制の例外として、次のような者は、公正証書の手続きを経ることなく、個人保証人となることができます。これらの者は、経営状況を把握し、保証によるリスクを認識できる立場にあると考えられるからです。
イ.融資を受ける法人の経営参画者
⇒ 融資を受ける法人の「理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」
ロ.融資を受ける法人の議決権総数の過半数を有する者(いわゆるオーナー)
ハ.融資を受ける者が個人事業者の場合、「共同して事業を行う者」又は「その個人事業者とともに事業に従事する配偶者」 |

※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |